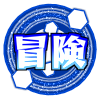;

|
海無鈴河 GM
剣と魔法のファンタジー! 皆さんに楽しんでいただけるような課題を探せるように頑張ります! ラブコメやコメディ、人情話など日常系が得意です! |
|||||
担当NPC
|
||||||
メッセージ村人になったら、ひたすら「ここは○○の村だよ!」って言いたい。 |
||||||
作品一覧 |
||||||
リンク
|
||||||
サンプルすべてが、荒れ果てていた。 遠くに大きな風車(ふうしゃ)が一基見える。かつて粉曳きに使われていたそれも、今では黙り込んだままだ。 「ここが……私の故郷……?」 大きな旅行鞄と真っ白な花束を持った少女――【エリゼ・シュライナー】が、ぽつりとつぶやいた。 穀物の名産地と呼ばれていたこの村は、12年前の大火ですべてを失った。 見渡す限りの畑も、集落をも飲み込んだ炎は三日三晩燃え続け、村人のほとんどは命を落とした。 のだが。 「エリゼは、運よく王国へ向かう商団に保護され、生き延びることができた……んだよね?」 小さな男子のような声がエリゼに尋ねる。声の主はエリゼの傍らに佇む黒い猫。エリゼは彼を【ミール】と呼んでいた。 エリゼは小さくうなずくと、かつて集落だったであろう場所に足を踏み入れた。 「本当に小さなころだったから全然覚えていないんだけど……なんとなく懐かしい気がする」 壁が焼け落ち、骨組みだけになった小さな家。水の枯れた井戸。心の隅の方に、ちくりと反応するものがある。 エリゼは自分の家はどこだったのだろうか、と考えながらさらに集落の奥へと足を進めた。 集落の最奥は広場になっていた。おそらく土地の祭などで使われていたのだろう。灰で煤けた赤い旗が、どこからか飛ばされてきた木材に引っかかっていた。そこだけ時間を止めたかのように、やけに鮮明で目に付く。 エリゼは旗を木材から外すと綺麗にたたんで抱えた。 広場の片隅にはこじんまりとした石碑がある。いや、石碑といえるほど立派なものでもない。ただ大きめの石をいくつか並べただけ。 石には『失われし村に捧ぐ』と文言が刻まれていた。 (誰かが作ったのかな) 命を落とした村人たちの鎮魂碑。エリゼは先ほどの赤い旗をその前にそっと置き、持参した花束を飾った。 膝をつき、手を組み、祈りをささげる。 「お父さん、お母さん。私、16歳になったよ。商団の元締めの家でお世話になってて、お手伝いもしてるんだ。……毎日楽しいよ」 エリゼは一度言葉を切った。エリゼの横で大人しくしていたミールが、ちょんと前足で彼女を突っつく。エリゼはミールに視線を向けると、覚悟を決めたようにうなずいた。 「私、魔法学園に入りたいの。魔法の勉強をして……知りたいことがあるの。あの火事の日、本当はなにがあったのか」 エリゼの脳裏に浮かんだのは、真っ赤に燃える炎。逃げろ、と叫ぶ父親の声。目の前で倒れた母親。 そして、母の背中は血に濡れていた。 「あの頃は何も考えられなかったけど、今なら分かる。あの日、火事以外に何かがあったんだって。……魔法学園は色んな人が集まるから、きっと何か分かることがあるはず。だから、お父さんお母さん。私を――」 見守っていてね、そう続けようとしたエリゼはぴたりと動きを止めた。 「エリゼ!!」 ちくり、と喉元に違和感がある。視線を下げると、ナイフがわずかに彼女の白い肌に食い込んでいた。 (誰……!?) 動かなくなったエリゼの耳元に声がささやいた。 「お前、今なんて言った?」 若い男の声だ。エリゼは慎重に答える。 「魔法学園に行く……」 「その前だ」 「えと……あの火事の日に、本当はなにがあったのか」 エリゼが答えると、男は尋ねた。 「お前、大火の生き残りか?」 「は、はい」 ナイフが喉元から離れた。エリゼは慌てて振り返り、男に対峙する。 「エリゼ、大丈夫!?」 「うん。ミール、大丈夫だよ……」 向き合った男は目深にかぶっていたローブのフードを外した。銀色の髪が風になびき、エリゼは一瞬それに目を奪われた。 (こんな綺麗な髪、街でも見たことない……) 「そういえば大火の生き残りが何人かいる、という噂は聞いていたな。……それがお前だったのか。名前は?」 「エリゼ・シュライナー……です」 男はそうか、とうなずくと突然エリゼの腕をつかんだ。 「え」 素早い動きにエリゼは身動き一つ取ることができなかった。 「おい、エリゼに何するんだよ!」 わあわあと叫ぶミールを一瞥すると、男は少し困ったような表情を浮かべた。 「悪いようにはしない。だから少し落ち着いてくれ」 「あの、本当にどういうことですか」 困惑したエリゼを見て、男は今度はしまった、と言いたげな表情になる。 「まだ名乗っていなかったか……。すまない。俺は【リヒャルト・レインズワース】。魔法学園に在籍している。そして、お前と同じく12年前の真実を追っている」 「え……!?」 思いもかけない言葉にエリゼは目を見開いた。腕を掴まれていることも忘れて、ぐいとリヒャルトの方へ身を乗り出す。 「ほ、本当ですか!?」 「あ、ああ……」 その勢いにリヒャルトは若干圧されながらもうなずいた。掴んでいたエリゼの腕をぱっと話すと、咳ばらいをひとつして表情を真剣なものに切り替えた。 「それで、提案だ。エリゼ・シュライナー、俺と一緒に魔法学園へ行かないか? 『12年前の真実を知る』。俺たちの目的は同じ。ならば手を組むほうがお互いのためになるだろう」 願ってもない話だった。商団の仕事で旅慣れていたとはいえ、エリゼも初めて向かう土地には不安もある。 (それに、あの日のことに少しでも早く近づけるなら……) 「エリゼ……大丈夫なの?」 ひょい、と肩に飛び乗ってきたミールが小声でささやく。 「……確信はないけど、彼なら大丈夫な気がする」 「エリゼの勘は当てにならないからなぁ……。まあ、ボクはエリゼについていくよ。なにかあったら守ってあげるし」 「ありがとう、ミール」 エリゼはミールに微笑むと、リヒャルトに改めて向き直った。 「お願いします。リヒャルトさん。……あの日何があったのか、真実を追いましょう」 |
||||||