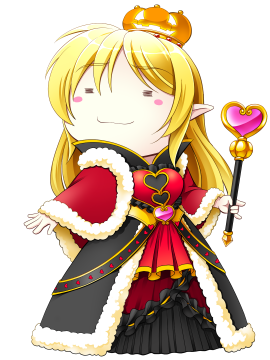|
|
《グラヌーゼの羽翼》エリカ・エルオンタリエ
エリアル Lv33 / 賢者・導師 Rank 1
|
|
エルフのエリアル。
向学心・好奇心はとても旺盛。
争い事は好まない平和主義者。(無抵抗主義者ではないのでやられたら反撃はします)
耳が尖っていたり、整ってスレンダーな見るからにエルフっぽい容姿をしているが、エルフ社会での生活の記憶はない。
それでも自然や動物を好み、大切にすることを重んじている。
また、便利さを認めつつも、圧倒的な破壊力を持つ火に対しては慎重な立場を取る事が多い。
真面目だが若干浮世離れしている所があり、自然現象や動植物を相手に話しかけていたり、奇妙な言動をとることも。
学園へ来る前の記憶がないので、知識は図書館での読書などで補っている。
|
|
| 装備
Equip
|
| メイン |
|
エーデンユート |
| 「エンディミオン」の強化品。様々な属性を持つ魔導書を宿した両手杖を更に精錬した一品。魔導書の力を発揮することで、通常攻撃をする際に「自然7属性」の内どれかの属性に変更することができる。 (イラスト:ルカ二IL) |
| サブ |
|
未装備 |
|
| ヘッド |
|
グロリアスヘッド |
| 【ゆうドラ】人の中で最も個性が出る箇所、それはどこか……。そう、フェイスだ。我が社のインターフェイスを見せられないのは残念だが、硬度だけでも一級品であることに変わりはないさ。 (イラスト:藤宮紅尾 IL) |
| ボディ |
|
巡日の鎧 |
| 5回目の全校集会に参加した記念に贈呈された鎧銅。贈呈用のため戦闘には向かないが、胸の部分には学園の校章が刻まれている。巡りし時を身に纏い、次の苦難を乗り越える勇者を讃えて。 |
| ハンド |
|
真紅の手甲 |
| 読み方は『クリムゾンガントレット』。ゴツゴツした質感は刃を通さず、この拳で殴られただけでも相手には被害を与えることだろう。やはり空調完備。 (イラスト:藤宮紅尾IL)(考案:桂木京介 GM) |
| フット |
|
ハッピータップ改 |
| より軽量化された、履いているとなぜか踊りたくなってくるブーツ。軽くて歩きやすい。 |
| アクセサリ |
|
クラウン・レプリカ |
| 6回目の全校集会の記念に用意された「クラウン・シーフ」練習用の王冠。レプリカとはいえ、意匠がこらされているので、カッコいい。 |
| ポケット |
|
正妻の制裁 |
| 魅了された者を正気に戻す道具。頬っぺたを引っ叩くことで「状態異常:魅了」を治す。 (イラスト:小鳥遊 巫鳥IL) |
| ポケット |
|
グラヌーゼ麦 |
| グラヌーゼ産のしっかりとした麦。ビールやパンなどの原料となる。 |
| ポケット |
|
未装備 |
|
| ルーム |
|
はねぱんだ |
| 学園に登録をされているはねぱんだの一体。セットすることで、エピソード中1回だけ呼び出す事ができ、任意の判定終了後ダイスを振り、以下の効果を生じる。1・2:自身のポケットのアイテムが1つ取られる(はねぱんだが使用する)。3・4:フムスを放ってくれる。5・6:5ターンの間すばやさを30増やしてくれる。(イラスト:L IL) |
|
|


|
|
《メメルの婚約者☆》仁和・貴人
ヒューマン Lv33 / 魔王・覇王 Rank 1
|
|
「面倒にならないくらいにヨロシクたのむ」
名前の読みは ニワ・タカト
身長:160㎝(本当は158cm位)
体重:45kg前後
好きなもの:自分の言う事を聞いてくれるもの、自分の所有物、メメたん
苦手もの:必要以上にうるさい奴
嫌いなもの:必要以上の労働、必要以上の説教
趣味:料理・・・だが後かたづけは嫌い
魔王っぽく振る舞っている
此方の世界の常識に疎い所がある
キャラとしてはすぐぶれる
物理と科学の世界からやってきた異邦人だが、かの世界でも世界間を移動する技術はなくなぜここに来れたのかは不明。
この世界で生きていこうと覚悟を決めた。
普通を装っているが実際はゲスで腹黒で悪い意味でテキトー。
だが、大きな悪事には手を染める気はない。
保護されてる身分なので。
楽に生きていくために配下を持つため魔王・覇王科を専攻することにした。
物欲の塊でもある。なお、彼の思想的には配下も所有物である。
服装は魔王っぽいといえば黒。との事で主に黒いもので固めていて仮面は自分が童顔なのを気にして魔王ぽくないとの事でつけている。
なお、プライベート時は付けない時もある
色々と決め台詞があるらしい
「さぁ、おやすみなさいの時間だ」
「お前が・・・欲しい」
アドリブについて
A
大・大・大歓迎でございます
背後的に誤字脱字多めなので気にしないでください
友人設定もどうぞお気軽に
|
|
| 装備
Equip
|
| メイン |
|
ペリドット・サイス |
| オリーブグリーンの刃を持つ大鎌。鮮やかな輝きが闇を吹き飛ばし、悪しきものから身を守ってくれる。この武器を装備している間、全ての属性不利を無効化する。 (イラスト:鈴木斗真 IL)(考案:海無鈴河 GM) |
| サブ |
|
未装備 |
|
| ヘッド |
|
グロリアスヘッド |
| 【ゆうドラ】人の中で最も個性が出る箇所、それはどこか……。そう、フェイスだ。我が社のインターフェイスを見せられないのは残念だが、硬度だけでも一級品であることに変わりはないさ。 (イラスト:藤宮紅尾 IL) |
| ボディ |
|
満月の天幕 |
| 「月の天幕」の強化品。妖しげなサーカス案内人をモチーフにした衣装。華やかなジャガード生地はミステリアスな雰囲気を醸しだし、闇の中でも目を引いてしまうだろう。より強い魔力を込めて縫合されている。(イラスト:けんと IL) |
| ハンド |
|
真紅の手甲 |
| 読み方は『クリムゾンガントレット』。ゴツゴツした質感は刃を通さず、この拳で殴られただけでも相手には被害を与えることだろう。やはり空調完備。 (イラスト:藤宮紅尾IL)(考案:桂木京介 GM) |
| フット |
|
C・de・S |
| 未来を司る精霊より授けられた足甲。歩く度地面に刻まれる証が旅を支えてくれる。装備中、5ラウンド毎に気力を30回復する。(イラスト:HUKIIL) |
| アクセサリ |
|
オーパーツ・レンズ |
| アンティーク風のデザインをしたゴーグル。エピソード内に1度だけ、射程4内に居る敵に対し、無属性魔法によるビームを発射することができる。 (イラスト:吉比IL) |
| ポケット |
|
高級なお肉 |
| トルミンで育てられたブランド肉「トルミン牛」。非常に柔らかい肉の繊維と、濃厚なのにさっぱりした後味が人気。 |
| ポケット |
|
身代わりうさぎ・改 |
| 気持ちのいい肌触りに思わず顔をうずめたくなるぬいぐるみ。ふわもこ感3割増し(当社比)。エピソード中2回まで、自身のダメージを代わりに受けてくれる。(イラスト:けんと IL) |
| ポケット |
|
未装備 |
|
| ルーム |
|
グリフォン アイテムEX
|
| 学園に登録されている一体を部屋で飼育させてもらっており、背中には2人まで乗れる。学生寮レベルが5以上かつ、ポケットに肉か魚のアイテムを装備時、エピソード中1回だけ「一般技能:生物騎乗のレベル×1ターン」の間自身と味方単体に強化状態「飛行」を付与する。滑落した等、効果が途中でなくなる場合がある)(イラスト:藤宮紅尾 IL) 仁和貴人のペット。
名はグリード。
性格は基本的には賢く素直である。
ただ、他のグリフォンとは喧嘩をすることも。
|
|
|