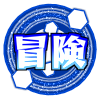;

|
桂木京介 GM
マスターの桂木京介です。 とうとう最終エピソードのリザルトノベルが納品されました。 長いようで短かった学園生活、いかがだったでしょうか。 物語はこれで終わりますが、生命のやどったキャラクターたちは、これからも長く人々の、もちろん私の記憶に残ることでしょう。 最後までお付き合いくださり、本当にありがとうございました! |
||||||||||||||||||||
担当NPC
|
|||||||||||||||||||||
メッセージ◇リザルトノベル公開中! 『さよならは、言わない』 最終エピソードです。 一人称、NPC、過去も未来も可能という特別中の特別エピソードでした。こちらの予想を大きく超えるバラエティ豊かなアクションプランの数々に胸を熱くしたものです。 皆さんどうかお元気で! |
|||||||||||||||||||||
作品一覧 |
|||||||||||||||||||||
リンク
|
|||||||||||||||||||||
サンプル |
|||||||||||||||||||||