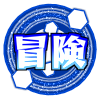;

|
K GM
GMに『K』と申します。 目標は、今、どこで、何が起きているのか、分かりやすい文章を書くこと。参加者様に楽しいひと時を提供することであります。 お知らせ、NPC一覧、随時ちょいちょい更新しておりますので、よろしければご覧くださいませ。 注意点:私は台詞等でアドリブを多く効かせるほうです。 それはNGですという方は、どうぞその旨をプランに明記してくださいませ。 NPC一覧 ―――――――― (人) アマル・カネグラ――豚のルネサンス少年。資産家の息子。村人・従者コース。小柄で太った眼鏡くんだがやたら強い。悪意はないが、ナチュラルに金持ち風を吹かす癖がある。 外見年齢12、3 髪/栗色 目/黒 肌/白 初出エピソード『【新歓】春、新入生、そして大掃除』 ルサールカ――ローレライの青年。カネグラ家専属の美術商であり詐欺師。服役していたことがある。美術品を強烈に愛す。目的のためなら平気で嘘をつく。一児の父。ラインフラウの息子。 外見年齢20代前半 髪/青 目/青 肌/白 初出エピソード『芸術クラブ放置施設――集え善意と金と物』 ガブ――三つ子その1:狼のルネサンス不良少年。魔王・覇王コース。見た目は体格のいい不良。威勢はいいが中身は単純、結構ヘタレ。サボり癖(最近は改善された)。子供に好かれる面もあり。以前アマルをパシリにしようともくろみ逆にパシらされていた黒歴史あり。セムに、使い勝手がよさそうな人間と見られ目をつけられている。 外見年齢15、6 髪/黒 目/黒 肌/褐色 初出エピソード『【新歓】春、新入生、そして大掃除』 ガル――三つ子その2:狼のルネサンス不良少年(以下同文)。魔王・覇王コース。 外見年齢15、6 髪/灰 目/灰 肌/褐色 初出エピソード『【新歓】春、新入生、そして大掃除』 ガオ――三つ子その3:狼のルネサンス不良少年(以下同文)。魔王・覇王コース。 外見年齢15、6 髪/茶 目/茶 肌/褐色 初出エピソード『【新歓】春、新入生、そして大掃除』 ドリャエモン――ドラゴニア老教師。相撲レスラー体形。お髭ふさふさ。常日頃から狼三兄弟の動向に頭を悩ませ、その指導を行っている。マン兄妹を養子に迎えた。魔王・覇王コース担当。 外見年齢70代前半 夫婦とも保護施設に、常駐職員として住んでいる。 髪/白 目/緑 肌/白 初出エピソード『芸術クラブ放置施設――リフォーム進行中』 セム・ボルジア――ヒューマンの若い女。観光業でその名を知られる。『ホテル・ボルジア』社長。買収や買いたたきが得意。サーブル城を観光施設にする野望を抱く。合理的で現実的。三度の飯より商売が好き。毒に詳しい。 親兄弟を毒殺した等、何かと悪評のある人物。味覚障害があるらしい。タバコをよく吸っている。 ボルジア一族は富の集積と一族争いを同時に引き起こす呪いがかかった、ノアの指輪を持っている。 そのために彼女の一家は彼女を除き全滅した。 トリス・オークとは、そりが合わない。とはいえ提携するべきときはする。 ラインフラウに無理心中させられかけ瀕死に陥ったが、生還。 外見年齢20代前半 髪/灰 目/灰 肌/白 (名前を出さない)初出エピソード『芸術クラブ放置施設――集え善意と金と物』 (名前を出しての)初出エピソード『サーブル城周辺調査隊、募集』 ラインフラウ――ローレライの(見た目)若い女。魔法使い。セムを骨の髄まで愛している。そのために黒犬たちの呪いを利用しようとしている。恋愛至上主義者。ルサールカの母(他にも3人子がいる)。セムと結婚したがっている(セムは拒否)。そのため赤猫と黒犬の呪いを利用しようとしたが、呪いが解けたため、果たせずに終わる。 セムを無理心中を強要し瀕死に陥ったが、生還。 外見年齢20代前半 髪/青 目/青 肌/白 初出エピソード『サーブル城周辺調査隊、募集』 トーマス・マン――村でリンチを受けているところ黒犬に助けられた少年。身柄学園預かり。黒犬を尊敬し、慕っている。最近ドリャエモンの養子になった。 芸能・芸術コースに入学。入寮している。 外見年齢10 髪/茶 目/茶 肌/白 初出エピソード 『ミラちゃん家――保護案件発生』 トマシーナ・マン――トーマスの妹。身柄学園預かり。ミラちゃんのお友達。最近ドリャエモンの養子になった。施設に来てからお料理が得意になった。 養父母のドリャエモン夫妻と施設に住んでいる。 外見年齢4 髪/茶 目/茶 肌/白 初出エピソード 『ミラちゃん家――保護案件発生』 カサンドラ――リバイバル。12年前に死んだ学園出身の高名な画家。グラヌーゼ出身。とても痩せている。存命の折は、自分の体が虚弱なことについて悩んでいた。 生前黒犬と繋がりがあった。彼と赤猫にかけられた呪いの解除法についても知りえていた。 しかしリバイバルになると同時にその記憶をなくしていた。 それを信じようとしない黒犬から、12年間追い回されていた。 学園に保護されて以来、徐々に記憶が取り戻されつつある。 ノアの呪いによって思考、言動を操られている疑い濃密。黒犬から騙されていた記憶を取り戻したことで、憤懣やるかたなく情緒不安定。 呪いの指輪を巡り、黒犬と衝突。いろいろ大変な目に遭ったが、最後は心穏やかに昇天した。 そして元気な赤ん坊として生まれ変わった。 外見年齢20代前半。 髪/金 目/青 肌/白 初出エピソード 『犬は荒れ野で狩りをする』 ウルド――家が焼き討ちされたところセムに助けられた、エリアル(フェアリータイプ)の少年。身柄学園預かり。 不思議な絵を描くのだが…… 外見年齢10 髪/銀 目/青 肌/白 初出エピソード 『王冠――新たな保護要請』 ロンダル・オーク――芸能・芸術コース所属。トーマスの嫌味な先輩でありライバル。実家はシュターニャにある。父親は不動産会社『オーク』の役員。 外見年齢12 髪/金 目/緑 肌/白 初出エピソード 『ある日ある時、食堂前でのひと騒ぎ。』 トリス・オーク――シュターニャにある不動産会社『オーク不動産』社長。ロンダルのおじさん。 外面と評判はいいが中身はかなり腹黒い。市の再開発に絡む問題で関係者1人、口封じのため殺したようだ。 セムとそりが合わない。とはいえ提携するべきときはする。 市会議員選に打って出るつもりらしい。 ―――――――― (魔物) 黒犬――犬をベースにノア一族が作った魔物。火を吐くでかい黒マスチフ。赤猫と仲が悪い。人(ヒューマン)に化けることが可能。ノア一族から赤猫ともども、命に関わる呪いをかけられており、それを解く手段を日々探している。 赤猫が嫌い。 去年の年末赤猫にボコられた。でも回復した。 外見年齢20後半(人に化けたとき) もしかすると、あまり頭はよくないかもしれない。 『ミラちゃん家――選択 』にて呪いが解け力と知力を失いただの犬になった。 トーマスのたっての願いにより、現在保護施設の番犬その2となっている。 髪/黒 目/黄色 肌/褐色 初出エピソード 『犬は荒れ野で狩りをする』 赤猫――猫をベースにノア一族が作った魔物。雷を起こすでかい赤猫。黒犬と仲が悪い。人(ヒューマン)に化けることが可能。ノア一族から黒犬ともども、命に関わる呪いをかけられている。常に泥酔している。呪いについてはうかつに触ると危険だと知っている。 黒犬が嫌い。 『ミラちゃん家――選択 』にて呪いが解け力と知力を失いただの猫になった。 現在セムの家に住み着いている。 外見年齢13、4(人に化けたとき) 髪/赤 目/緑 肌/白 初出エピソード『猫は夜中に踊りだす』 ピク太郎――ミミックのミミ子に貢ぐため小銭を集めるピクシー。 外見年齢7、8。 髪/金 目/青 肌/白 初出エピソード『ピクシー×ミミック』 ミミ子――ピク太郎に貢がせるゆるふわ系ミミック。 かわいい家の形をした貯金箱。1000000000Gためられる。 初出エピソード『ピクシー×ミミック』 ―――――――― (精霊) スイカマン――頭がスイカの競泳パンツをはいたイケメン。夏の浜辺に出没し勝手にライフセーバーをしている。 外見年齢 二十代前半。 初出エピソード『夏の浜辺のスイカマン』 ミラ様=ミラちゃん(正式名:ミラージュ)――学園保護施設の守護精霊。光の形で出現し、姿はない。時と場合によって、ミラ様と呼ばれたりミラちゃんと呼ばれたり。よく光の粉を噴く。 生き物を癒し、育てる力を持つ。ちょっと恥ずかしがりやさん。 施設関係者に貰った単語カードによって、意思を伝えてくる。 (名づけ前)の初出エピソード『春、新入生、そして大掃除』 (名づけ後)の初出エピソード『芸術クラブ放置施設――絶賛リフォーム進行中』 ―――――― |
|||||
担当NPC
|
||||||
メッセージ2022・5・23 最後のリザルトが承認されました。 これにて私の「ゆうしゃのがっこ~」での活動は終了いたします。 これまで当エピソードにご参加くださった方、まことにありがとうございました。 またどこかでお会いできましたら、そのときは改めてよろしくお願いいたします。 追伸:最後のプランにてねぎらいのメッセージを下さった方、ありがとうございました。 ―――― 2022・4・28 次回、エピソード公開は5・7。 このエピソードが、『ゆうしゃのがっこ~』GMとしての最後の仕事になります。 ―――― 2022・4・15 次回エピソード公開は4・20。 王冠シリーズ、ラストとなります。 ―――― 2022・3・29 次回エピソード公開は4・4。 王冠シリーズの続きです。 ※色々ありまして、当シリーズは4月内に終了する予定です。 急転直下に駆け足な展開となりますことお許しください(´ `:) ―――― 2022・3・11 次回エピソード公開は3・18. 王冠シリーズの続きです。 ―――― 2022・2・23 次回エピソード公開は3・3。 日常。学園の思い出を文字として残そう――的なお話。 ―――― 2022・2・21 ファンレター一通、お受け取りしました。 お送りくださった方、ありがとうございます。m(_ _)m ――――― 2022・1・9 次回エピソード公開は2・16。 王冠シリーズの続きです。 ―――― 2022・1・22 次回エピソード公開は1・31。 廃業した喫茶店を再生(?)させようプロジェクトです。 ―――― 2022・1・6 次回エピソード公開は1・15。 王冠シリーズの続きです。 ―――― 2022・1・3 あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いします。 『ゆうしゃのがっこ~』もフィナーレが見えてきましたが、それまでにシリーズを完遂……出来なかったらすいません(TωT;) ―――― 2021・12・24 次回エピソード公開は公開は12・31。 あけましておめでとうな、日常話の予定です。 ―――― 2021・12・10 次回エピソード公開は公開は12・16。 『王冠』シリーズの続きです。クリスマス前夜あたりのお話。 ―――― 2021・11・21 次回エピソード公開は公開は12・1。 トーマスの学園生活におけるもめごとに、関与する話になる予定です。 ―――― 2021・11・9 次回エピソード公開は11・16。 単発魔物退治以来となります。 ガブ、ガオ、ガルが出ます。 ―――― 2021・10・28 次回エピソード公開は11・1。 もう一つの呪いの指輪(セムが持っているもの)についての話が始まります。 ―――――― 2021・10・19 ファンレター一通、お受け取りしました。 お送りくださった方、ありがとうございます。m(^ ^)m ――――― 2021・10・13 次回エピソード公開は10・17。 トーマスのこれからに関わるお話になる予定です。 ―――― 2021・9・25 次回エピソード公開は10・1。 芸術の秋。 PCさんから提案がありました、アマチュア限定参加の展覧会を開催いたします。 ―――― 2021・9・12 次回エピソード公開は9・17になる予定。 黒犬が再び出てきます。 ただの犬としてですが。 ―――― 2021・8・25 次回エピソード公開は、9・1を予定。 休憩の日常回になります。 スイカマンが出る手筈です。 ―――――― 2021・8・7 次回エピソード公開は、8・16を予定。 ミラちゃん家シリーズ、事実上のクライマックス回になりそうです。 ―――― 2021・7・25 次回エピソード公開は、7・31を予定。 ミラちゃん家、続きとなります。 指輪問題に、セム方面の問題が食い込んでくる予定。 ―――― 2021・7・7 次回エピソード公開は、7・15を予定。 ミラちゃん家、続きとなります。 呪いの解除方が明らかになる予定です。 ―――――― 2021・6・25 ファンレター一通、お受け取りしました。 お送りくださった方、ありがとうございます。m(_ _)m ―――――― 2021・6・22 次回エピソード公開は、6・29を予定。 ミラちゃん家エピソード、続行となります。 赤猫再度が動くかもです。 ―――― 2021・6・4 次回エピソード公開は6・13となります。 ミラちゃん家の続きです。 緊迫したエピソードになります予定。 ―――― 2021・5・21 次回エピソード公開は5・28となります。 ミラちゃん家、続きです。 呪いの指輪は無事手に入れましたので、今後は呪いの謎解きに挑むこととなります。 ―――― 2021・5・4 次回エピソード公開は5・12となります。 ミラちゃん家はちょっと休憩。 とある村を困らせている魔物を追い払うという、簡単な課題です。 ―――― 2021・4・19 次回エピソード公開は、4・27となります。 指輪を探しにグラヌーゼ遠征。 保護施設居残りルートもあります。 ―――――― 2021・4・5 次回エピソード公開は、4・12となります。 ミラちゃん家の続き。 指輪についての情報集め、追加の分です。 ―――――― 2021・4・1 ファンレター一通、お受け取りしました。 お送りくださった方、m(_ _)m ありがとうございます。 ―――――― 2021・3・19 次回エピソード公開は、3・28となります。 ミラちゃん家休憩の意味で、お花見日常エピソード。 NPC、大体揃って出ています。 ―――― 2021・3・5 次回エピソード公開は、3・13となります。 ミラちゃん家、プチリフォームいたします。 ファンレター、一通お受け取りいたしました。 お送りくださった方、ありがとうございます(^ ^)。 ―――――― 2021・2・26 ファンレター一通、お受け取りしました。 お送りくださった方、ありがとうございますm(_ _)m。 ―――― 2021・2・17 次回エピソード公開は、2・26となります。 ミラちゃん家、黒犬との第二回会談が始まる予定です。 ―――― 2021・2・4 次回エピソード公開は、2・11となります。 久しぶりにミラちゃん家、日常です。 少しはまったり出来るといいのですが。 ―――― 2021・1・28 2020・1・13より、この場でのファンレター受け取り報告が途絶えていたことに今気づきました。 今日までの間にファンレターをお送りくださった方、ありがとうございます。そして大変申し訳ございません……どうかご容赦を。(T T)。 お受け取りしましたものは、欠かさず読ませていただき、今後のエピソードを作る上での参考にしております。 最後に受け取り報告が遅れましたこと、重ねてお詫び申し上げます。まことにすみませんでした。 ―――― 2021・1・19 次回エピソード公開は、1・26となります。 引き続き、ミラちゃん家。 赤猫サイドのお話です。 ―――――― 2021・1・11 次回エピソード公開は1・12となります。 ミラちゃん家の続きです。 例の本のありかを突き止める回です。 ―――――― 2021・1・2 またしても出遅れましたが、皆様、新年あけましておめでとうございます。 願わくば本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 ―――――― 2020・12・21 次回エピソード公開は12・27となります。 皆でクリスマスを豪華に、あるいは質素に楽しもう……という内容です。 公開日がイベント出遅れ感ありありですが、そのあたりはどうかご容赦下さいませ(´ `;)。 ―――――― 2020・12・8 次回エピソード公開は、12・12となります。 ミラちゃんシナリオです。 黒犬が赤猫と接触事故を起こす模様。 ―――――― 2020・11・25 次回エピソード公開は11・28となります。 少し休憩、の意味で日常シナリオです。現在進行形の犬猫案件とリンクしてはいますが。 ガブガルガオ三兄弟が出てきます。 ―――――― 2020・11・17 下記に掲載しました現在公開中のエピソード「ミラちゃん家――新たな始まり」の抜けた第一章について。 今確認いたしましたところ、抜けが解消しておりました(^ ω^)! 参加者の皆様、まことにお騒がせいたしました。m(_ _)m ―――――― 2020・11・14 現在公開中のエピソード「ミラちゃん家――新たな始まり」について。 すみません、今確認いたしましたら、第一章が抜けたまま公開されておりました…orz。 私のミスか、それとも不具合が原因なのか、今のところどうもはっきりしませんが、ひとまずのところ以下に、抜けた部分を掲載しておきます。 ・・・・・・・・・・・・・ ●グラヌーゼは今日も雨だった 複数ある『果て無き井戸』のひとつ。 堅牢な丸い石組みを囲っていた青草は忍び寄る冬の圧力によって茶色く枯れ萎び、くたりと地面に伏していた。そのせいで夏より視界がぐんと開け、寂寞感がいや増している。 そこに後から後から降り注ぐ、冷たい雨。 【ラインフラウ】はレースの傘をクルリと回し『いいお天気ね』とうそぶいた。皮肉ではない。本日は井戸へ近づくに当たって、格好のお天気なのだ。雨が降る日、猫は外に遠出しないものだから。 レインコートに身を包んだ【セム】は、手にした大きなカゴを降ろした。カゴの中には猫が数匹、落ちつか無げに動き回っていた。どれも平凡な容姿をしている。そのへんの町角から適当に集めてきたのだから、当然だ。全部が全部、首輪を着けられている。小さな涙の形をした石……通信魔法石『テール』の欠片だ。 セムはカゴのカギを外し、蓋を開ける。 「さあ、好きなところに行きなさい」 猫たちは降ってくる雨に不快さを示しつつカゴから飛び出し、次々井戸の中へ入って行く。その様にセムは、感心したような息を漏らした。 「皆、よくためらわずあの中へ入って行きますね。初めて見る場所のはずなのに」 ラインフラウが笑って言った。 「本能的に分かるのよ、シャパリュが近くにいるということが。それにしても猫にテールをつけて送り込む。それで盗聴を行うなんてね。あなたらしい思いつきよ。そういうの好きだわー」 熱っぽい眼差しを注いで、セムにしなだれかかる。濡れるのも構わずに。セムはそれにあまり構わずタバコに火をつけ一服し、井戸を見つめた。 「様子を観察して話せそうな相手だと判断出来たなら、こちらからも呼びかけますよ。まあ、どこまでうまくいくか分かりませんけどね。あの程度の大きさの石では1回こっきり、数時間しか使えないし――それ以前にシャパリュが、あの猫たちを仲間と認めず殺してしまうかもしれないし」 ・・・・・・・・・ 不手際、真に申し訳ありません…(T T;)。 ―――――― 2020・11・13 ファンレター一通、確かにお受け取りしました。 お送りくださった方、ありがとうございますm(^ ^)m。 ―――――― 2020・11・8 次回エピソード公開は11・12となります。 ミラちゃん家、新しい段階に入ります。 黒犬との直接会談が行われます。 ―――――― 2020・10・27 次回エピソード公開は10・30となります。 ミラちゃん家の続き。 トーマスたちの今後を決める回となりそうです。 ―――――― 2020・10・14 次回エピソードは10・17公開となります。 メインはゴブリン退治ですが、裏には赤猫がちらついております。 狼三兄弟が出ます。 ―――― 2020・10・2 次回エピソードは、9・3公開となりました。 先に申しましたとおり、黒犬案件と相成りましてございます。 ―――― 2020・9・28 システム的問題が解決いたしました。 リザルトが遅れないように頑張ります。 ―――― 2020・9・27 ファンレターが一通届きました。 お送りくださった方、ありがとうございますm(_ _)m。 ―――― 2020・9・26 現在システム的な問題が発生しまして、出発済みエピソード「サーブル城周辺調査隊、募集」のプランが確認できない状態になっております。 数日中に問題は解消されるとは思いますが、リザルトは遅れるかも知れません…参加者者の皆様申し訳ないです(T T;)。 次回エピソードは、黒犬がまた出る予定です。公開日が決まりましたら、またここでご連絡いたします。 ―――― 2020・9・13 次回エピソードは、9・17に公開となります。 サーブル城付近への遠征課外授業となります。 ―――― 2020・9・1 ファンレターが一通届きました。ありがとうございます(^ω^)。 ―――― 2020・8・28 ファンレターが一通届きました。ありがとうございます(^ω^)。 次回エピソードは9・3頃に公開となります予定です。 保護施設のお話、続きです。 ―――― 2020・8・20エピソード公開予定。 タイトルは「夏の浜辺のスイカマン」 ほぼほぼ何も考えなくていいコメディです。 ―――― ファンレター、いつもありがたく受け取っております。 暖かいご声援、感謝です。 |
||||||
作品一覧 |
||||||
リンク |
||||||
サンプル桜色の髪をしたエリアルの令嬢【ソリン・アスク】は、大きな姿見をのぞき込んだ。 若葉色の瞳は夢見るようにぼうっと潤み、白い頬には赤みが差している。指でひっきりなしにいじりまわしているせいで、髪の毛先にカールがついてしまっているが、彼女本人はそんなこと全く気づいていなかった。 現在ソリンの頭の中は、一人の男でいっぱいなのだ。 その男というのはローレライ。名前は【ギンナル】。澄んだ水のような青い髪と青い瞳を持ち、すこぶる整った風貌の青年。 一月前、川辺で出会った瞬間から彼女はもう、彼に恋しているのである。お熱なのである。 (すてきな人……あんな人、これまで会ったことがないわ……顔はきれいだし、服の趣味も洗練されてるし、言葉遣いは丁寧だし、それに何より、楽しくお話ししてくれる。このあたりにいる男連中とは、全くもう、天と地ほどの段違い……) そんなことを考えながら甘いため息をついていた彼女は、エリアルの特徴である尖った耳をぴくりと動かした。どすどすという足音が聞こえてきたのだ。 控えめなノックの音。同時に、太い声。 「ソリン、ソリン、おるかのう」 興をそがれた顔付きになったソリンは、声のトーンを下げて返事した。 「なーに、お父様。何のご用事」 扉が開く。 顔を見せたのは、彼女の父親たるドラゴニア【ファグニル・アスク】。 人間種ながら純種に近い部分を多く残す部族の出身で、顔かたちが少々人間離れしている。 体の色は黒に近い褐色、目の色は金色。湾曲した角、顔の半分ほどを覆う鱗。巨大な翼、といかにも恐ろしげな容姿だ。 しかしてその実体は、心配性なパパなのである。 「いや、ぜひお前に会わせたい者がいてな」 切り出された一言目ではや、相手が何を言わんとしているか察するソリンは、間髪いれずに返した。 「いい、会いたくない。どうせまたそのへんの『将来有望そうな青年』を捕まえてきたんでしょう。前も言ったじゃない、私、まだお見合いなんかする気はないって」 「いやいやいや、そう深刻に受け止めずともいいのだソリン。わしも見合いとまでは考えておらぬ。お前はまだまだ若いのだから。ただな、将来のことを考えて、今からいろんな相手に会っておくのは大切なことだと思ってな。ゆくゆくはそのうちから、一番いいと思うのを選べばよろしい」 ああ、またか。そう思ってソリンは、眉間を狭めた。本当にこれで何回目だろう。どうせまた全然自分の好みじゃない相手を連れて来たのだ。お父様は。 「実質お見合いじゃないの……あのねお父様、そういうのもう本当にいらないから」 「そんなことを言うものではないソリン。確かにお前は見合いするには早いくらい若い。しかし、自分の将来について考え始めねばならん年頃ではあるのだぞ。実はもう庭先まで足を運んでもらっておるでの、とにかく一目、一目見るだけでもいいのだ。お前も気に入るだろう。実にいい若者だぞ」 なんとか娘の関心を呼び起こそうと、父親は長々、己が眼鏡にかなう相手の美点について説き聞かせる。 「健康でたくましく、誠実で勇敢な若者だ。体術にも剣術にもよく通じておる。これまでに屠った魔物はおよそ50……」 しかしそうやって説けば説くほど、娘の気持ちは冷めていく。これまでの経験から、いやというほど知っているのだ、父親が「いい若者」だと押してくる相手が、自分にとってそうだった試しがないということを。 誰も彼も無骨で、戦い以外に興味がなくて、退屈な人間ばかり。自分が嬉しくなったり楽しくなったり面白くなったり出来るような気の聞いた台詞、一言だって言えやしない。そんな相手と結婚なんて考えられない。私が好きなのは、もっと全然別なタイプの人だ。何故お父様はそれを分かってくれないのか……。 「とにもかくにも会うだけはしなさい。ソリン。ちらっとだけでもいいから」 かようなことを娘が考えているとも知らず父親は、根気よく自分と一緒に来るように説き続けた。 そこに、彼の強力な味方が遣ってくる。ソリンの母親であり彼の妻である【リト・アスク】だ。娘同様エルフ型のエリアル。つややかな若葉色の髪と瞳をした美しいご婦人だ。 「ソリン、お父様を困らせるものではありません。とにかく、会うだけは会いなさい。お客様は、遠いところから足を運んできてくれたのですよ……それなのにあなたの顔も見せずに返すなんて、礼儀から考えて、出来た話ではありません」 と言っている母の後ろからぬうっと、ファグニルに良く似た姿かたちの若者が顔を出す。ソリンの兄、【スケグル・アスク】だ。父同様困った顔をして、妹にこう言ってくる。 「ソリン、お客様は庭で、お前のことをずっと待っておられるぞ。そうやって意地悪をするものではない。気の毒ではないか」 父のみならず母、おまけに兄からまでそう言われると、ソリンもさすがに無視できない。渋々鏡の前から神輿を上げ、庭に出て行く。言い忘れたが彼女の家は、それはもう立派なものだ。火山岩を組んで作られた、まさしく難攻不落の城砦である。庭というのもだだっ広い。その気になれば一連隊の閲兵式を行うことだって出来るくらいだ。 何を隠そうアスク家は、広大な火山連山一帯に名を轟かせる豪族なのだ。魔王との戦において勇者達から『火炎の翼』と称された一ドラゴニアが始祖とされる。 その始祖が残した家訓『質実剛健』『謹厳廉直』を一族郎党は、二千年この方ずっと守り続けている。外から嫁や婿をとる場合も、その基準に適うものしか駄目、という方針でやってきた――とくると、必然的に『結婚相手はドラゴニアしか認められない』という流れになってしまうし事実そうだったのだが、この数百年外部との交流が進められたこともあって、ようやく意識が『結婚相手はドラゴニアでなくとも、ドラゴニアの子が成せる相手ならばよい。ただし質実剛健で謹厳廉直な人間に限る。』というところまで変化してきている。 その象徴が、現当主ファグニルの妻、および息子、娘の存在だ。 ファグニルは若い頃武者修行として、大陸各地を転々と渡り歩いたことがある。 それにより彼は、様々な経験をした。ヒューマンが信念を貫きえること、エリアルが勇壮でありえること、ルネサンスが深い知恵を持ちえること、ローレライが信義を重んじえることを知った。自分がこれまで信じてきた世界の形は、ただ一方向から見えたものに過ぎないことを深く悟った。 そしてエリアルの女を愛するに至り――結婚したのだ。 その結婚に眉を潜める一族は、当時多かった。なにもわざわざ当主が異種族の女を娶らずともいいではないかと。弱い子が出来てしまう、と。 しかしそういった言葉はリトがアスク家に来てから、すぐ立ち消えた。なんとなれば彼女が見た目に反し、超剛健なことが分かったからである。 実のところリトは、周辺の森一帯に名を轟かせる女戦士だったのだ。最低限自分と同格かそれ以上の腕を持つ男と添いたいと常より思っていたが、条件にかなう相手が周辺になかなか見つからずいたところ、ファグニルと出会い意気投合。進んで嫁入りした次第。 ――とはいえそんな昔話、ソリンにとってはどうでもいい。 庭に出ていった彼女を待っていたのは、予想通りな容貌のドラゴニア青年だった。肩幅広く逞しく、顔かたちも無骨で、絵に描いたような質実剛健振り。 ソリンの可憐さを目の当たりに上がってしまったのか、話し振りもどもりどもり。 「せ、拙者クロニア連山を納めるガリアーシュ家の嫡男、ドラーギアでござる。このたびは名高いソリン姫に、僭越ながらご挨拶に参りました次第……姫様は実に、実にご機嫌麗しくそのうあのう」 ソリンはもう退屈でしょうがない。良家の子女らしくお客を無視するようなことはせず、微笑を浮かべ適当に相槌を打ったりするのであるが、その実ほとんど相手の話を聞いていない。 |
||||||